今、J-POPが破竹の勢いで世界を席巻しつつあります。
YOASOBI、Creepy Nuts、新しい学校のリーダーズ…日本の若い世代の絶大な支持を集める彼らの人気は、国境を越え、世界的なものになりつつあります。
YOASOBIは、ビルボードの全世界ランキング1位、Google検索「Song」カテゴリー世界1位、YouTubeの世界楽曲チャート1位を全て獲得するという快挙を成し遂げました。Creepy Nutsの「Bling-Bang-Bang-Born」は、世界31カ国のランキングにチャートインし、再生回数は7億回を超えています。新しい学校のリーダーズは、北米ツアーの11都市全てを瞬く間にSOLD OUTし、業界関係者たちを驚かせました。
かつてJ-POPは、東洋的な魅力こそあれ、決してグローバル・スタンダードにはなれないと言われてきました。
しかし今や世界中のリスナー、特に10代から20代の若い世代に、熱狂的に受け入れられ、新たなグローバル・トレンドとなりつつあるのです。なぜ僅か10年程の間に、これほど劇的な変化が起こったのでしょうか。
その理由を、YOASOBIを始めとする若いミュージシャンたちの音楽的ルーツに立ち返って考えていくと、ある共通のキーワードに行き着きます。
「ボーカロイド」
YOASOBIのコンポーザー、Ayase氏は、もともとボーカロイド、通称「ボカロ」の楽曲を制作するクリエーター「ボカロP」でした。それは彼の音楽的アイデンティティでもあります。彼自身、「ボカロをやってきていることが、僕のベースには大事なものとして残っている」と語っています。
今や、海外で聴かれる日本の音楽上位100曲の1/4をボカロ曲が占めているといいます。この数字は、ボーカロイドが世界的な普遍性を獲得し、漫画やアニメ、ゲームと並ぶ「日本文化の新たな象徴」になりつつあることを示しています。
なぜソフトウェアによって作られた人工的な歌声が、これほどまでに国境や言語の壁を越え、人々の心を深く掴むのでしょうか。

世界的な楽器メーカーであるヤマハ株式会社は、様々なアナログ楽器のデジタル化事業の総仕上げとして「歌声」のデジタル化、つまり「歌と楽器の境界を消すこと」に挑戦しました。そして2003年、歌声合成ソフトウェア「VOCALOIDTM」を世に送り出しますが、大きなムーブメントを生み出せずにいました。どんなに高度な音声処理技術を駆使しても、「ヒトと機械の境界」を消し去ることができずにいたのです。
しかし、2007年、その境界は、たった一人の「ツインテールの女の子」によって消し去られます。
その名は「初音ミク」。
札幌の小さなソフトウェア企業クリプトン・フューチャー・メディアが開発したバーチャルシンガーは、その印象的なビジュアルと、それまで誰も耳にしたことのない唯一無二の不思議な歌声によって、瞬く間に日本の若い世代の間に広がります。
かつての音楽業界は、大手レーベルに見出されたひと握りの才能だけが、多額の制作費と大々的なマーケティングを通じて作品を世に届ける世界でした。クリエーターとなり、自分の歌や曲を広く聴いてもらうためには、才能、運、人脈、そして資金力という「社会の境界」を乗り越えなくてはならなかったのです。
しかし、初音ミクは、この境界をあっさり消し去ります。
パソコンとネットワーク、そして数万円のソフトさえあれば、誰もが楽曲を制作し、歌わせ、世界に向けて発信できるようになったのです。音楽業界とは無縁の人たちが、プロデューサーを意味する「P」を付けて「ボカロP」と名乗り、次々と創造性を解き放ち始めました。プロとアマチュアの垣根は取り払われ、大手レーベルの力に頼らずとも、その才能が評価され、支持される世界が拓けたのです。
その影響力は、音楽制作の門戸を広げるだけにはとどまりません。音楽表現の常識を根底から変える「革命」を引き起こします。
クリエーターたちが手にした「思いのままに創る自由」は、これまで「人間が歌う」という大前提に縛られてきた作曲の常識すらも、あっという間に打ち破ります。
その象徴的な作品が、2008年に発表されたボカロ曲『初音ミクの消失』。初めて聴く方は、圧倒的な情報量に度肝を抜かれることでしょう。
常識では考えられないようなハイテンポで叩きつけられるのは、1秒間におよそ10文字という、人間には到底真似のできない超高速の歌唱。
「何を歌っているのか、全く聴き取れない歌」
しかし、この曲は、当惑する大人たちを尻目に驚異的な再生回数を記録します。
それまでの「歌」の概念を打ち壊す、型破りな表現ですら許されることを、鮮烈に印象付けました。
ボーカロイドは、もはや「人間の代役」ではなく、クリエーターの表現欲求に応えるための新しい「楽器」であり、新たな表現手段となったのです。声域、息継ぎ、滑舌といった物理的な制約から完全に解放されたクリエーターたちは、それまでは不可能と思われていた複雑なメロディーや超人的な技巧を、思うがまま楽曲に盛り込めるようになりました。
初音ミクは、プロとアマの壁だけでなく、「歌と楽器の境界」や「伝統と創造性の境界」をも消失させたのです。

ボーカロイドは、様々な境界を消し去り、音楽文化の解放者となりました。しかし、そこには最も根源的な問いが残ります。
「なぜ、感情を持たない機械による合成音声が、これほどまでに人々の心を打ち、深い共感を呼ぶのか?」という謎。
ボーカロイド文化の研究者たちは、この謎を解くため、世界中のリスナーを対象に聞き取り調査を行いました。そして、予想外の結果を目の当たりにします。
リスナーたちは揃って、「ボーカロイドの歌声は自身の感情によって変わる。悲しい時、嬉しい時、辛い時、その時々で違って聞こえる」と答えたのです。
予想外の結果に戸惑いつつも、研究者たちは一つの結論に達します。
初音ミクを始めとするボーカロイドは「リスナーが自分の感情を投影できる“空っぽの器”」なのだと。
人間の歌手には、その歌声と共に、人格、経歴、ルックスといった「個性」が伴います。私たちは音楽を聴くとき、無意識にその「個性」と歌声を結びつけて聴いています。しかし、ボーカロイドには実体がありません。それ故にリスナーは、歌い手の個性を自分自身で創造し、その世界観に没入できます。
ボーカロイドの「全てを受け入れる無個性」は、リスナーの創造力が入り込むための「余白」として機能します。そしてリスナーが、その「余白」に自らの感情を注ぎ込むことは、「自分の心が投影された曲」にアレンジすることでもあります。それはちょうど、鏡に写った自分の内面を見つめ直すのと同じ意味を持つでしょう。
「余白」がリスナーの心を映し出す鏡となり、そこに映し出された自分の内面が感情を揺さぶるからこそ、ボーカロイドは言語の壁を越え世界のリスナーの心を掴んだのではないでしょうか。
この「余白」を尊び、「余白」を心の鏡と考える哲学は、日本人特有の感性に深く根差したものだと考えることもできます。
日本の伝統芸術には、あえて描き切らず、語り尽くさず、受け手の想像力に委ねることを尊んできた歴史があるからです。
ボーカロイドの「無個性」は、能の感情表現に例えることができます。
能楽では、演者が能面を被ることで表情と感情を隠し、「無個性」を生み出します。
観客は、その「余白」に自身の感情を映し出し、能面の陰影の変化や、演者の所作から、主人公が訴える浮世の無常と無念の想いを、自分事として感じ取るのです。
表情を隠す能面が、観客自身の感情によって埋められる「余白」であるならば、合成音声特有の無個性によって「余白」を生み出し、リスナーの心を映し出す鏡となるボーカロイドは、「インターネット世界の能面」であると言っても過言ではないでしょう。
しかもインターネット上の存在であるが故に、リスナーを受動的な存在から能動的な存在へも変容させます。動画配信のコメント機能によって、リスナーは創作に参加することが可能になります。これはコンピュータ&ネットワーク時代の「リアルタイムなコミュニケーションによって、常に変化し進化する文化」だからこそ実現した、創作の新たなカタチです。
リスナーは、コメントを通じて応援や批評をすることで、楽曲から受け取った感情を言語化し、物語の解釈者、そして楽曲の音楽世界の拡張者として余白を埋めていきます。
ボカロPという「第一の創作者」が曲を作り、バーチャル歌姫初音ミクが「第二の創作者」として歌い、リスナーが自らの感情と解釈を投影することで余白を埋める「第三の創作者」となる。この三位一体こそが、ボカロ文化の核心であり、人々を深く惹きつけてやまない魅力なのではないでしょうか。

ボーカロイドは、プロ・アマの垣根を取り払い、人間という物理的な制約から解き放ち、誰もが創造主になれるという革命を成し遂げました。そしてその深層には、「余白」に価値を見出す日本の伝統的な美意識が息づいていました。それは、最新技術と日本の文化背景の融合が生み出した「奇跡」だと言えます。
そして今、その奇跡は新たな局面を迎えています。
近年、より人間らしい歌声合成AIが次々と登場しています。それらは、驚くほど自然な歌声を生成し、クリエーターの労力を大幅に削減する可能性を秘めています。冒頭でご紹介した「VOCALOIDTM」や「初音ミク」も年内にはAI版がリリースされる予定です。
しかしここで、一つの懸念も浮かびます。AIによる徹底したリアリティの追求は、ボーカロイドの魂とも言える「余白」を奪ってしまうのではないか、あまりに人間らしく感情豊かに歌い上げることで、リスナーが感情移入する隙間が消失し、「空っぽの器」でなくなってしまうのではないかという懸念です。
しかし、一方では新たな可能性も見えてきます。AIが「余白」を奪うのではなく、クリエーターがその「余白」をデザインするための、より強力な魔法の杖ともなり得るということです。
例えば、「喜びの中に微かな寂しさが混じる」といった抽象的なイメージをAIに与えるだけで、AIがそのニュアンスを解釈し、適切な歌唱パターンを生成することによって、クリエーターは大きな労力が必要な微調整から開放され、これまで以上に繊細で複雑でクリエイティブな表現をできるようになるでしょう。
さらに、AIはリスナーと音楽の関係性をも変える可能性も秘めています。リスナーの心拍数や表情をリアルタイムで読み取り、曲の展開や歌声のニュアンスをインタラクティブに変化させる、「リスナーと対話する歌」も夢物語ではないでしょう。それは、リスナーを「第三の創作者」から、音楽とリアルタイムで共鳴し合う「共演者」へと変える新たな可能性です。
技術は常に進化します。しかし、その技術をどう使いこなし、どのような価値を見出すかは、いつの時代も人間に委ねられています。ボーカロイドが「余白」という文化的な価値と結びついたように、これからのクリエーターはAIという新たなツールと対峙し、その中に新たな「余白」や表現の可能性を見出していくに違いありません。ボーカロイドという真っ白なキャンバスの上で、無数のクリエーターとリスナー、そしてAIが共鳴し合い、まだ誰も聴いたことのない、新しい時代のココロの歌を描き続けていくことでしょう。私たちの未来には、無限の真っ白い余白が広がっているのかもしれません。
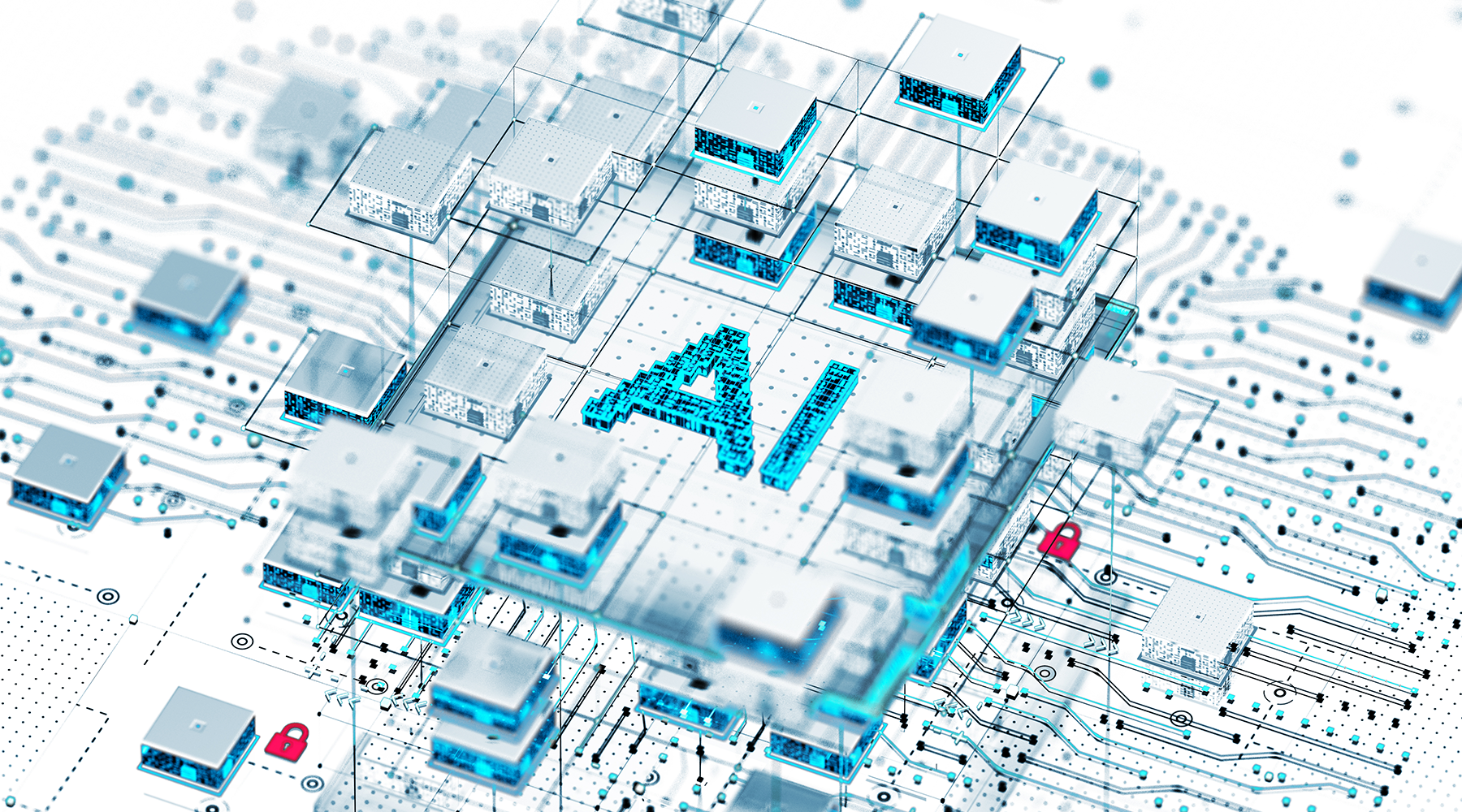
[1] ヤマハ株式会社「VOCALOIDTM公式サイト」
https://www.vocaloid.com/anniversary/
[2] i4U「AIと人間が高め合う創造性の未来——「初音ミク」生みの親、伊藤博之氏に聞く音楽×AI時代の展望」
https://i4u.gmo/CgEXy
今回はボーカロイドがテーマでしたので、筆者お薦めのボカロ曲を幾つかご紹介して締めくくらせていただきます。
『余熱』 / MIMI feat. 初音ミク
https://youtu.be/5uHtY6DpRi4?si=cIj9v2zu3zRHwr1o
『カエダマ』/サンテツfeat. 重音テト
https://youtu.be/cbyic6uDL_U?si=9vfZDPz2XwCbIyDK
『シンカンセンスゴイカタイアイス - 東海道新幹線60周年フアンメイドムービー』/ Shannon feat. 初音ミク & GUMI & 歌愛ユキ
https://youtu.be/O_VRIuKM9gw?si=E8Iobx2noqhiwz8_
『サイエンス』 / MIMI feat. Synthesizer V AI 重音テト
https://youtu.be/m-bvW4pKT68?si=fU2AbBBkz0a-WuIC
※「VOCALOID(ボーカロイド)」「ボカロ」ならびに「VOCALO CHANGER」はヤマハ株式会社の登録商標です。
製品についてのお問い合わせやご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。
本サイトのお問い合わせフォームならびにお電話にて受け付けております。