「「あと一回だけ!」
じゃんけん、テレビゲーム、あるいは大事な商談。私たちは日常のあらゆる場面で「勝負」に直面します。
そして、多くの人がこの経験則を知っています。
「なぜか、負けが込み始めると、泥沼にはまったかのように連敗してしまう」
「さっきはあの選択で失敗したから、今度は絶対に違う方を選ぶぞ」
「相手はさっき強気だったから、今度も同じパターンで来るはずだ」
そう思えば思うほど、ツキは逃げていく。焦れば焦るほど、判断は鈍る。私たちは、この不可解な「負けの連鎖」を、運やコンディションのせいにしてしまいがちです。
しかし、もしそれが「運」ではなく、あなたの「脳のクセ」が原因だとしたら?
「勝負に勝ちたければ、過去を引きずるな」。これは単なる精神論ではありません。最新の脳科学研究が裏付けた、極めて実践的な「勝利のための戦略」なのです。

西シドニー大学などの研究チームが、非常に興味深い論文を発表しました。彼らが解き明かそうとしたのは、非常にシンプルかつ本質的な問いです。
「競争的な意思決定において、勝つ人と負ける人の脳の働きは、具体的にどう違うのか?」
この問いに答えるため、研究チームは「じゃんけん」という、私たちにとって最も身近なゲームを実験に用いました。
なぜ、じゃんけんなのか?
それは、じゃんけんが「人間の思考のクセ」を炙り出すのに最適なモデルだからです。
じゃんけんの必勝法は、理論上ただ一つ。「完全にランダムであること(予測不可能であること)」です。相手が何を出すかに関わらず、自分がグー・チョキ・パーを完全に1/3ずつの確率でランダムに出し続ければ、理論上の勝率は5割(あいこを除く)に収束します。
しかし、私たち人間は、この「完全にランダム」というのが恐ろしく苦手です。無意識のうちに「(なぜか)グーを出しがち」だったり、「勝ったら次も同じ手を出す」「負けたら手を変える」といった、特定の戦略やパターンに陥ってしまいます。
研究チームは、この「人間特有の予測可能な偏り」が、脳のどの情報処理によって引き起こされているのかを突き止めようとしました。
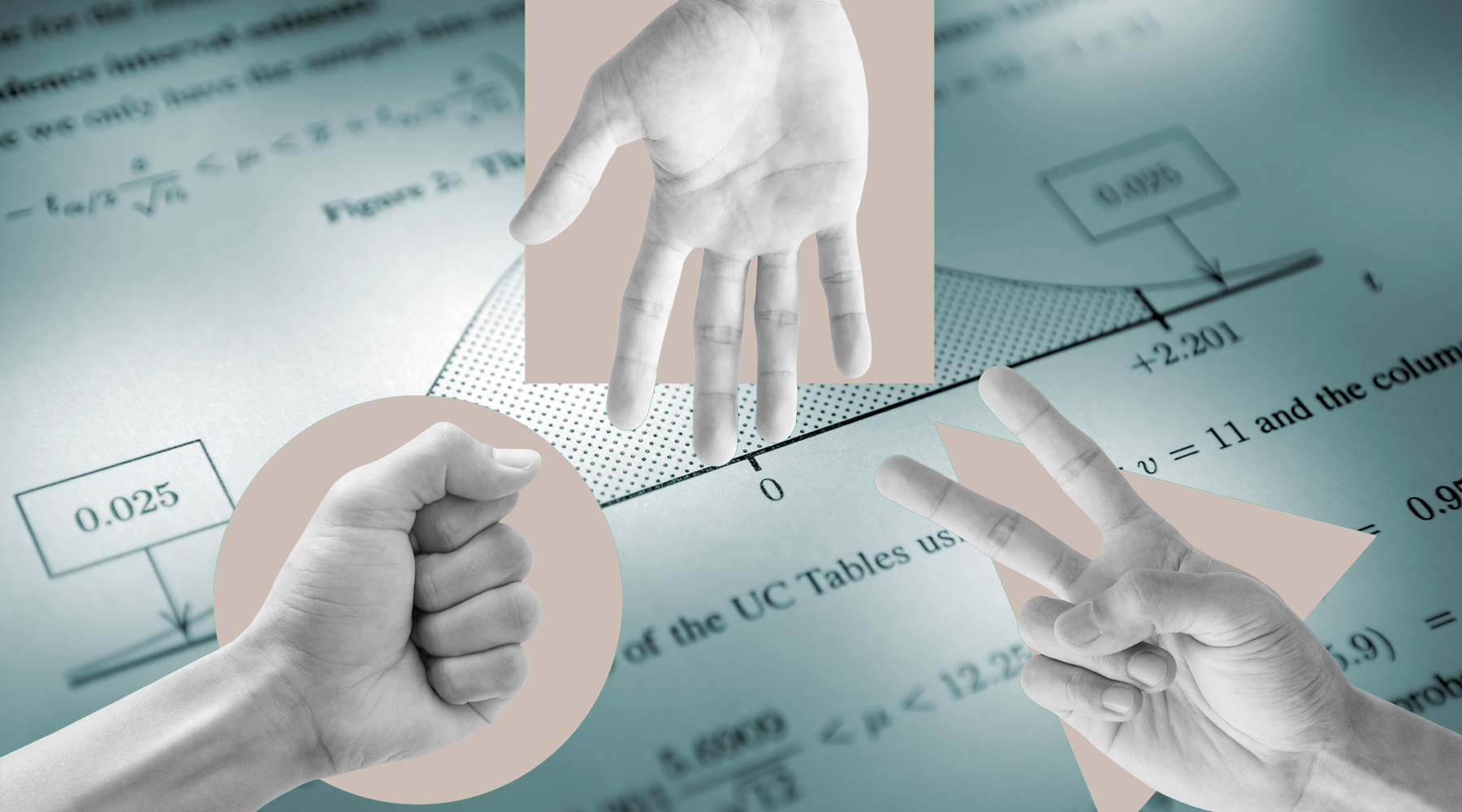
研究は「ハイパースキャニング」という最先端の手法を用いて行われました。これは、2人の人間がリアルタイムで「じゃんけん」という社会的交流を行っている間、両者の脳活動(この研究ではEEG:脳波)を同時に記録する技術です。
31組(62名)の参加者が、コンピューター上で何百回もじゃんけんゲームをプレイしました(この実験の被検者にはなりたくありませんね⋯)。研究チームは、その膨大な脳波データを「多変量デコーディング」というAI(機械学習)のような技術で解析し、彼らの脳がその瞬間、「何を考えていたか」を読み解いたのです。
具体的には、以下の4つの情報が、脳内でどのように処理されているかを時系列で追跡しました。
今、何を出そうとしているか
相手が何を出すと予測しているか
一つ前の勝負で、自分は何を出したか
一つ前の勝負で、相手は何を出したか
解析の結果、勝利の女神が微笑む「脳」の秘密が、残酷なまでに明らかになりました。
まず、「今、どの手を出すか」という現在の意思決定に関する脳の活動は、最終的な勝者も敗者も同じように活発でした。どちらも真剣に「今の手」を選んでいたのです。
決定的な違いは、「過去の情報」の扱いにありました。
試合の「敗者」の脳だけが、自分の「前の手」と相手の「前の手」の情報を、次の手を決める段階(意思決定フェーズ)で強く保持し続けていたのです。
これが何を意味するのでしょうか?
まさに、冒頭で挙げた「負けが込む人の思考」そのものです。
「前の手が頭に浮かぶ人ほど、最適なランダム性から離れ、思考に偏りが強まって相手に読まれやすくなる」
研究者らは、この「過去の試行に関する情報の保持」こそが、ランダム(予測不可能)であるべき最適なパフォーマンスを妨げた、つまり「負け」に直結した可能性が高いと結論付けています。
「さっきはグーを出したから、次はチョキにしよう(=自分の前の手に縛られている)」
「相手はさっきパーを出したから、今度はグーで来るかもしれない(=相手の前の手に縛られている)」
こう考えた瞬間、あなたはもう「ランダム」ではありません。あなたの思考は「過去」という名のノイズに汚染され、特定の思考パターン(偏り)を生み出します。相手が賢ければ、そのパターンは即座に読まれてしまうのです。
一方で、勝者の脳は違いました。彼らの脳は、驚くほど「今」に集中していました。過去の情報を引きずっていなかったのです。だからこそ、よりランダムに、より予測不可能に行動でき、結果として勝利を収めたと考えられます。

「いや、それはたかがじゃんけんの話でしょう?」と思うかもしれません。
しかし、この「負け(失敗)が続くと冷静さを欠き、過去の結果に固執して、現在の最適な判断(=ランダム性=客観性)を見失う」という脳の傾向は、勝負ごとだけでなく、私たちの日常のあらゆる判断や行動のクセとして潜んでいます。
プレゼン中、あるスライドで言葉に詰まってしまったとします(=1回の負け)。
あなたは「まずい、失敗した」「さっきのところ、変に思われたかも」と、過去の失敗を頭の中で反芻し始めます。
その結果、どうなるでしょう?
今、話しているスライドへの集中力を完全に欠き、声は上ずり、表情はこわばり、さらにミスを重ねてしまいます。これは「敗者」の脳と同じく、過去のトライアル(前の手)に縛られ、現在のパフォーマンス(今の手)を台無しにしている典型例です。
逆に「勝ち」に縛られることもあります。「前回、このジョークで場が和んだから、今回も使おう」と、状況や聴衆が全く違うのに「過去の成功(前の手)」に固執し、スベってしまうのも同じ現象です。
パートナーや同僚との議論中、相手から過去の失敗を蒸し返されたとします(=相手の前の手)。
あなたは「よくもあの時のことを言ったな!」「そっちこそ、あの時こうだったじゃないか!」と、意識は「今」の議題ではなく、「過去」のその一言にロックオンされます。
その結果、相手が今、何を話し、何を解決しようとしているのかが耳に入らなくなります。あなたはただ、相手の「前の手」に対して、いかに反撃するかだけを考えてしまう。これでは、建設的な結論(=関係性の勝利)に至るはずがありません。
「あの時、あのプロジェクトは大失敗したから、似たような案件は絶対に避けるべきだ(=自分の前の負け)」
「前回はこのやり方で過去最高益が出たから、今回も同じ方法でやるべきだ(=自分の前の勝ち)」
これらはすべて、過去の「勝ち」や「負け」に意思決定を歪められている状態です。市場や状況は刻一刻と変化しているのに、「前の手」にこだわるあまり、今、この瞬間に最も合理的で最適な判断ができなくなっているのです。
「あの部署はいつも非協力的だ(=相手の前の手)」というレッテル貼りも同様です。過去の経験がバイアスとなり、「今回は協力してくれるかもしれない」という客観的な可能性を潰してしまいます。

では、過去の呪縛から逃れ、勝負に強い「勝者の脳」を手に入れるには、どうすればよいのでしょうか。この研究は、私たちが様々な課題や仕事に取り組むべき「思考と姿勢」を明確に示唆しています。
それは、「一回ごとのリセット(メンタル・リブート)」を意識的に行うことです。
この研究の勝者は、「前の手」の情報を脳内で保持していませんでした。私たちも、一つの仕事や交渉が終わったら、その結果が良くても悪くても、いったん強制的に思考をリセットします。
「さっきは最悪のプレゼンだった」ではなく、「さて、次の会議の準備だ」と捉えるのです。
具体的には、「一度立ち上がって水を飲む」「窓の外を見て深呼吸する」「『さて、』と声に出して次のタスク名を言う」など、物理的な行動を挟むことで、脳は「前のフェーズ」が終わったと認識しやすくなります。
じゃんけんでの「ランダム」は、ビジネスや人生においては「バイアスのない客観的な判断」と言い換えられます。過去の成功体験(勝ち)や失敗体験(負け)という強力なバイアスを捨て、目の前の課題を「これが初めての挑戦だ」という新鮮な目で見つめ直すことが、勝利への最短距離です。
「前回はこうだった」ではなく、「今、状況はどうか?」「今、使えるリソースは何か?」と、常に「今」を主語にして考えるクセをつけましょう。
プレゼンでミスをしたり、議論で言い負かされたりした時こそ、チャンスです。「あ、まずい。今、自分は『敗者』の脳になっているな」と自覚してください。脳が「前の手」を反芻し始めたら、それは危険信号です。
一度、思考を止めましょう。相手の話を遮ってでも「少し整理させてください」と一呼吸置くのです。冷静さを欠いたまま次の手を打つことこそ、連敗への入り口です。
「メンタル・リブート」の「秘訣」は、一つの魔法のような方法があるわけではなく、自分に合った「切り替えスイッチ」のバリエーションを用意しておくことが大切です。
じゃんけんで負けが込む人は、脳が「過去」でいっぱいになっています。
人生でうまくいかない時、私たちの脳は「あの時の失敗」「あの人から言われた一言」でいっぱいになっています。
この研究が教えてくれるのは、真の強さとは、過去の膨大なデータから複雑な戦略を練ることではなく、「過去を手放し、今この瞬間、まっさらな脳で最善の一手を打つ」という精神的なタフネスと思考の柔軟性である、ということです。
次の勝負が始まったら、もう「前の手」を思い出すのはやめにしましょう。
あなたの「今」は、過去の延長線上にある必要はないのです。
[1] Social Cognitive and Affective Neuroscience 「Neural decoding of competitive decision-making in Rock-Paper-Scissors」
https://academic.oup.com/scan/advance-article/doi/10.1093/scan/nsaf101/8269262?login=false
製品についてのお問い合わせやご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。
本サイトのお問い合わせフォームならびにお電話にて受け付けております。