「親が特定の動画ばかり見て、話が通じなくなった」
「友人が急に『メディアは嘘だ』と力説し始めた」
身近な人が突然、信じがたい「陰謀論」の世界に深くハマっていく姿に、戸惑いを覚えた経験はありませんか?
これまで、この現象は個人の性格や思考の問題だと考えられがちでした。しかし、それだけでは、なぜ多くのごく普通の人々が、まるで「何かに目覚めた」かのようにその世界観に没入するのかを十分に説明できません。
ある社会学の研究は、この現象を「個人の問題」ではなく、社会的なプロセスとして捉え直しています。キーワードは「共鳴」。人々が陰謀論を信じる過程を、段階的に深まる「共鳴的目覚め」として描き出しているのです。
このコラムでは、この研究を手がかりに、ごく普通の人が陰謀論に染まるメカニズムを3つのステップで解き明かします。そして、冷静な人ですら陥る「共感の罠」と、私たちがこの複雑な情報社会を生き抜くヒントについて考えていきたいと思います。

そもそも、なぜ人は「別の物語」を求めるようになるのでしょうか。その入り口は、多くの場合、とても個人的で、切実な体験にあります。研究によれば、多くの人が最初に経験するのは、専門家や公的機関といった「信じていたはずの権威」への信頼が、根底から覆されるような出来事です。
論文に登場する80代の男性ピーターさんの「目覚め」は、家族が医療ミスで亡くなるという悲劇から始まりました。深い悲しみと怒りは、やがて「医療システムそのものが信頼できない」という大きな不信感へと変わっていきます。「専門家を信頼していたのに裏切られた。その時から、私は物事を疑い、自分で調べ始めたんです」と彼は語ります。
彼らの経験は特別なものではありません。信頼していた人からの予期せぬ仕打ち、組織の不誠実な対応。こうした「裏切られた」という強い感情的な経験は、これまで当たり前だと信じてきた社会の仕組みに対する、根本的な疑いを生み出します。
この段階で生まれるのは、「何かがおかしい」「きっと真実が隠されているはずだ」という強い疑念と、答えを探し求める渇望です。研究では、この感情の揺さぶりを「感情的共鳴」と名付けられています。
それは、既存の秩序に対する不協和音を心の中に響かせ、人々を「本当の答え」を探す旅へと駆り立てる最初のエンジンです。この出発点は「非合理的」だからではなく、むしろ深い痛みから生まれ非常に「人間的」な反応であり、誰の身にも起こりうる第一歩なのです。

個人的な痛みと不信感から始まった「探求の旅」は、どのようにして陰謀論への確信へと変わっていくのでしょうか。論文は、そのプロセスを「共鳴」が連鎖していく3つの段階として説明しています。
これは、すべての始まりの段階です。医療、政府、メディアといった権威への信頼が失われることで生まれる、ショックや怒り、不信感。この強烈な感情が、公式な説明ではどうしても納得できない、という感覚を生み出します。「もしかして、この世界は嘘に満ちているんじゃないか?」という感情的な揺さぶりこそが、人々をこれまでとは違う「答え」を受け入れる準備をさせる原動力となります。
感情的な探求の末に、人々は「答え」に出会います。それが陰謀論です。陰謀論は、彼らの漠然とした不安や怒りに対し、「誰が本当の敵で、一体何が起きているのか」を説明する、分かりやすく感情に訴えかける物語を提供してくれます。
ある人は、特定の陰謀論に触れた時を、「まるで頭の中で電灯がパッとついたように、物事がはっきりと見えた」と表現します。複雑な社会問題が、たった一つの物語でスッキリと説明される。この「謎が解けた!」という感覚こそが「認識的共鳴」です。
そして、この段階で決定的に重要なのは、その「発見」が孤独な作業ではないという点です。陰謀論を信じる人は、孤立してPCに向かう人をイメージされがちですが、実際はその逆。「認識的共鳴」は仲間との交流の中で爆発的に増幅されるのです。
オンラインのコミュニティでは、まず自分たちの個人的な体験談(原因不明の体調不良など)を共有し、「自分だけじゃなかったんだ」という連帯感が生まれます。そこに「専門家が隠している証拠」とされる情報が投下されると、個人の不安は一つの大きな物語へと回収され、興奮と一体感に包まれます。仲間とSNSでメッセージを交わしながら、関連動画を同時に視聴し、衝撃や怒りをリアルタイムで共有する。
こうした経験を通じて、彼らは「共に真実に目覚めた仲間」という強い絆を育んでいきます。この段階で、陰謀論は単なる「情報」から、仲間との繋がりを確認し合うための社会的なツールへと変わるのです。
「答え」と「仲間」を得た人々は、物語の受け手だった状態から、自ら参加し、行動を起こす「活動家的共鳴」の段階へ進みます。
多くの人が始めるのが「自分なりのリサーチ」です。しかし、これは科学的な視点で仮説を検証する作業ではなく、自らの信じる物語を裏付ける情報を探す旅になりがちです。ネットの広大な情報の中から信念を補強してくれる断片を見つけては仲間と共有し、確信をさらに強固なものにしていきます。
さらに、彼らは自ら物語を拡張し始めます。元々の陰謀論の「空白」の部分を、自身の専門知識や解釈で埋め、独自の説を構築し、発信していくのです。
このように、自らが物語の創造に関わることで、「真実を暴くヒーロー」というアイデンティティを獲得し、コミュニティ内で承認されていきます。そして、その使命感は、やがてデモなどの具体的な社会活動へと向かうこともあるのです。
この3ステップ ― 感情の揺さぶりから始まり、物語と仲間に出会い、そして自らが行動する主体となる ― を通じて、「共鳴」は雪だるま式に大きくなり、かつての個人を、揺るぎない確信を持つ活動家へと変貌させていくのです。
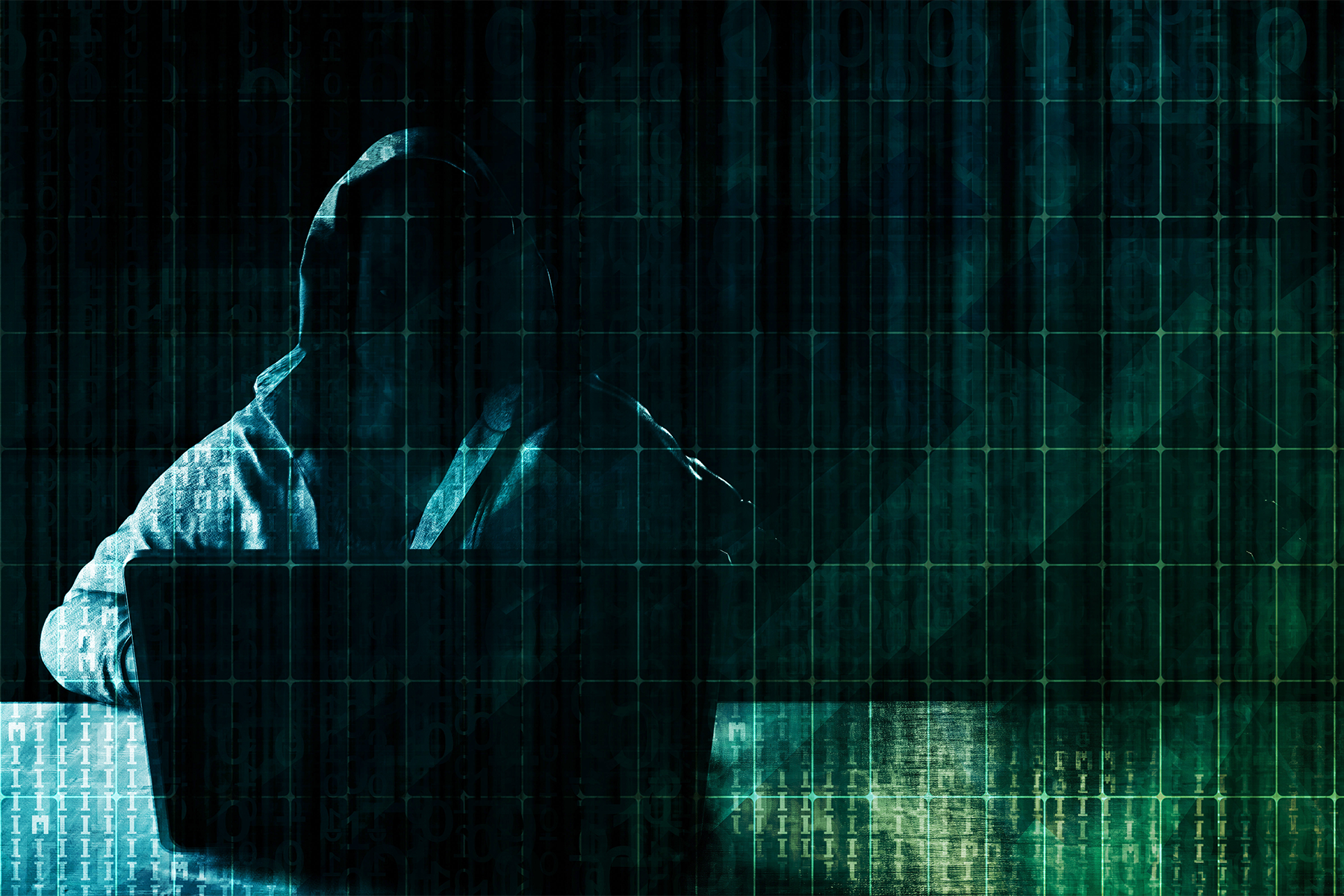
このプロセスを知ると、「なぜ、冷静で知的な人ですら巻き込まれてしまうのか?」という疑問が浮かびます。陰謀論には論理的な矛盾や事実誤認が多く含まれるにもかかわらず、なぜ多くの人が、論理的な正しさよりも仲間との“共感による納得感”を優先してしまうのでしょうか。
その答えは、人が単にロジックだけで生きているわけではない、という事実にあります。「共鳴」のプロセスは、孤独感を埋め、承認欲求を満たし、「自分は真実に目覚めた特別な存在だ」というアイデンティティを与えてくれるなど、強力な社会的・感情的な見返りをもたらします。
一度この心地よいコミュニティに所属してしまうと、抜け出すのは簡単ではありません。陰謀論に疑問を呈することは、仲間との絆や自分の大切な居場所、アイデンティティそのものを否定することに繋がりかねないからです。論理的な正しさよりも、この温かい繋がりを失う恐怖が、矛盾から目を背けさせてしまうのです。
さらに、彼らの出発点が「権威への不信」であるため、専門家からの論理的な反論やファクトチェックは、むしろ「やはり権力者が真実を隠そうとしている証拠だ」と解釈され、信念をさらに強固にする燃料になってしまいます。こうして、正論よりも「仲間との共感」が優先される、閉鎖的なループが完成するのです。

この現象は、決して他人事ではありません。SNSのアルゴリズムによって、誰もが自分に心地よい情報ばかりに囲まれ、論理よりも共感を優先してしまう危険性と隣り合わせの時代に生きています。では、どうすればこの罠を避けられるのでしょうか。
「社会的な出来事に強い怒りや不安を感じた時、すぐに分かりやすい「敵」や「物語」に飛びつかないこと。「なぜ自分はこれほど強く反応しているんだろう?」と一歩引いて、自分の感情の源を見つめる時間を持つことが大切です。
自分が信じることとは違う、批判的な視点や情報源に意図的にアクセスする習慣を持ちましょう。「自分なりのリサーチ」が、いつの間にか自分の考えを補強する情報ばかりを集める「確証バイアス」に陥っていないか、常に意識する必要があります。
現代社会が抱える問題の多くは非常に複雑で、唯一絶対の「正解」がないことの方がほとんどです。「すぐに分からなくてもいい」と受け入れる知的な謙虚さが、単純すぎる物語への逃避を防いでくれます。
もし身近な人が傾倒してしまった場合、頭ごなしに否定するのは逆効果です。その人の根底にある個人的な痛みや社会への不信感に耳を傾け、信頼関係を断ち切らないことが重要です。その上で、少しずつ異なる視点を提示していく、長い対話が必要になります。

今回ご紹介した研究は、陰謀論にハマる人々を「理解不能な人」として切り捨てるのではなく、彼らが経験する人間的な苦悩や、社会的な繋がりを求める心から生まれるプロセスとして描き出しました。
「目覚め」の物語は、複雑な世界に秩序と意味を与え、仲間との「共鳴」は、孤独な個人に居場所と目的意識をもたらします。それは、時に非常に強力な引力となります。この問題は、個人の知性の問題である以上に、社会全体の信頼が揺らいでいることの表れなのかもしれません。
不確かな情報が溢れる社会で、私たちは何を信じ、どう行動すればいいのか。この問いは、防災という領域で、信頼できるデータを通じて社会の安全を守ろうとする私たちの姿勢にも深く繋がっています。
私たちにできるのは、複雑な課題から目をそらすことなく、確かな事実に基づいて粘り強く思考すること。そして、心地よいだけの閉じたコミュニティに安住せず、異なる意見を持つ他者との「対話」を続けていくこと。
このコラムが、皆さんと社会との関わり方を考える、一つのきっかけになれば嬉しく思います。
[1] 【元論文】Resonant Awakenings: The Social Lives of Conspiracy Theorists
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00380385251344483
製品についてのお問い合わせやご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。
本サイトのお問い合わせフォームならびにお電話にて受け付けております。