ふとした瞬間に友人のことを思い出したら、その直後に彼から電話がかかってきた。「これは虫の知らせだ」「テレパシーかもしれない」 ― そんな風に胸がざわついた経験は、誰にでもあるのではないでしょうか。
「噂をすれば影」という言葉があるように、私たちは日常の中で起こる「偶然の一致」に、特別な意味や物語を見出したくなります。それは人間らしいロマンチックな感性であり、人生を豊かにするスパイスでもあります。しかし、スペイン・バルセロナ大学の研究チームが2025年に発表した最新の研究は、この「偶然に過剰な意味を見出す脳のクセ」こそが、私たちが疑似科学や根拠のないデマ、陰謀論といった「情報の沼」にハマり込む入り口である可能性を科学的に示唆しました。
バルセロナ大学の研究チームが行った実験は、非常にシンプルでありながら、人間の認知の根源的な欠陥を浮き彫りにするものでした。研究の目的は、ホメオパシーや占星術、超能力といった「疑似科学的信念」を持つ人々と、そうでない懐疑的な人々との間に、どのような認知処理の違いがあるのかを検証することでした。
今回は、この興味深い心理学研究を紐解きながら、私たちの脳が抱える「確率やランダム性に対する致命的な弱点」を明らかにします。そして、情報が氾濫する現代社会において、私たちがこの「脳のバグ」をどのように補正し、賢く、そして騙されずに生きていくべきかについて、具体的かつ実践的な思考法を考えます。
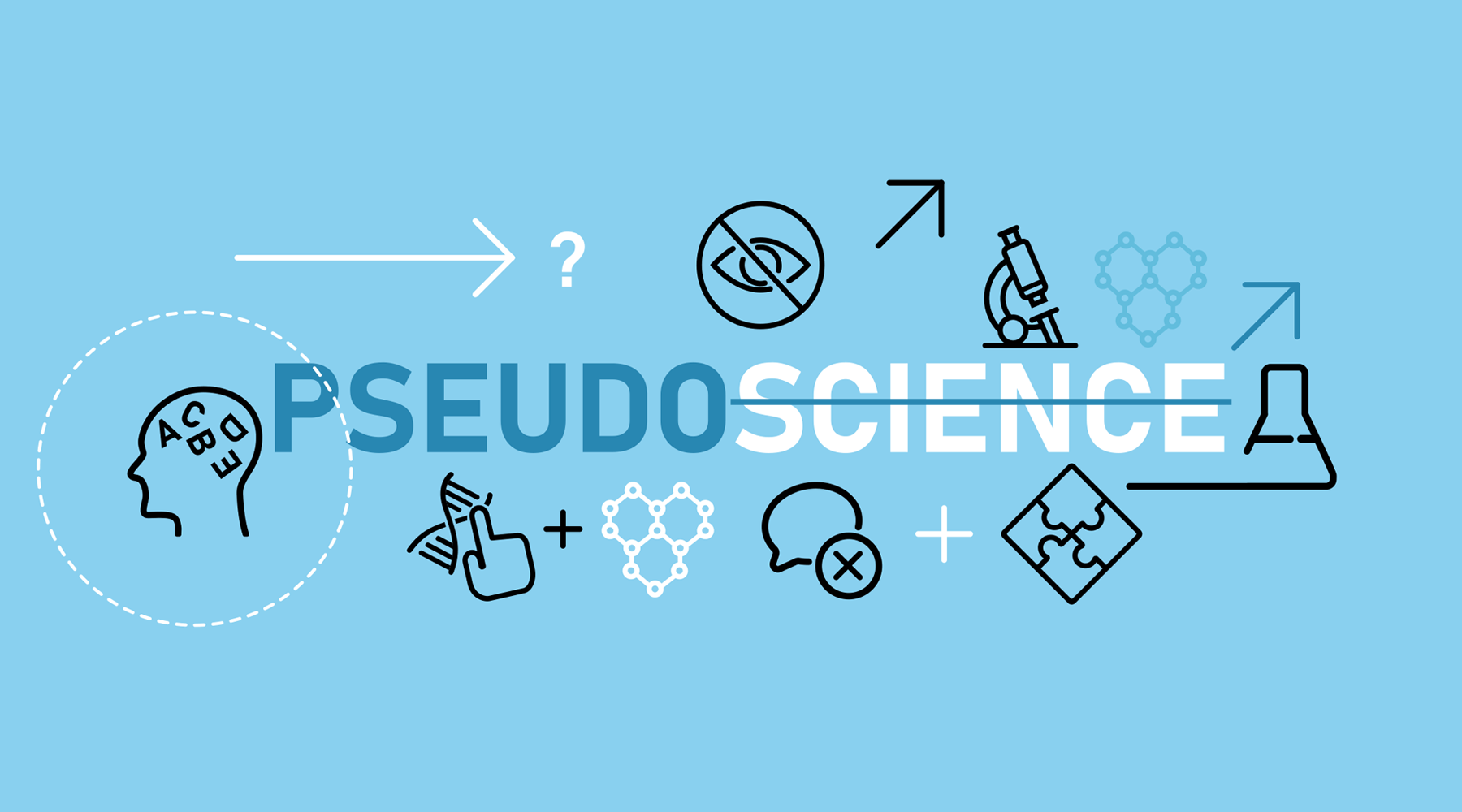
研究チームは、108名の大学生を対象に調査を行いました。まず、参加者の「疑似科学を信じる度合い(PESスコア)」を測定し、日常でどれくらい「不思議な偶然」を体験するか、そしてその原因をどう考えているか(単なる偶然か、運命や神の介入か)を質問しました。
さらに、ここからがこの研究の白眉ですが、参加者に「コイン投げ」と「サイコロ振り」をコンピュータ上でシミュレーションしてもらうタスクを行わせました。「本物のコインを投げたときのように、ランダムに見える裏表の並びを作ってください」と指示したのです。
その結果、驚くべき傾向が明らかになりました。
疑似科学を強く支持する人ほど、自分で作った「ランダム」な並びにおいて、同じ結果が続くこと(「表・表・表」など)を極端に避ける傾向があったのです。
本来、コインを投げれば「表」が3回、4回と続くことは確率的に十分にあり得ます。しかし、疑似科学を信じやすい人々の脳内にある「ランダムのイメージ」は、「表・裏・表・裏・表」のように、きれいにバラついた状態に偏っていました。これを心理学では「反復回避バイアス」と呼びます。
このバイアスが強いと、現実に「表」が連続して出たとき、それを「自然なランダムの結果」として受け入れられず、「何らかの作為がある」「流れが変わった」「特別な力が働いている」と誤認しやすくなります。つまり、彼らは「偶然」を正しくシミュレーションできないがゆえに、現実の「偶然の偏り」を「必然(運命)」と誤読してしまう、つまり「反復回避バイアスの罠」にハマってしまっていたのです。
この「ランダム性の誤解」と「偶然への過剰な意味づけ」は、単なるコイン投げの話では終わりません。研究チームは、この認知メカニズムが、健康や医療に関わる重大な判断ミスに直結していると指摘しています。

論文の中で挙げられている「ホメオパシー(成分が含まれないほど希釈されたレメディなどを投与する代替療法)」の例を見てみましょう。
あなたは頻繁に頭痛に悩まされています。ある日、友人から「この錠剤(ホメオパシー)がいいよ」と勧められ、試してみることにしました。すると、飲んだ直後に頭痛がすっと消えました。
このとき、私たちの脳は強烈な「成功体験」としてこれを記憶します。「薬を飲んだ(原因)」から「治った(結果)」という因果関係を瞬時に結びつけるのです。
しかし、冷静に考えてみれば、頭痛というものは時間の経過とともに自然に治まることが多いものです。つまり、薬を飲まなくてもそのタイミングで治っていた可能性(自然治癒)があります。
ここで「反復回避バイアス」や「偶然への意味づけ」が強い脳は、この「たまたま治るタイミングと服用のタイミングが重なった(偶然の一致)」という可能性を棄却してしまいます。「こんなにタイミングよく治るなんて、偶然のはずがない。薬の効果だ!」と飛びついてしまうのです。
一度そう思い込むと、次からもその薬を使い続け、「治った回」ばかりが記憶に残り、「治らなかった回」は無視されるようになります。こうして、客観的には効果のない治療法が、その人の主観的な世界の中だけで「特効薬」へと昇格し、場合によっては適切な標準治療を受ける機会を遅らせるという悲劇を招くのです。
研究チームは、疑似科学的信念を減らすためには、単に科学知識を教え込むだけでなく、この「偶然の解釈」と「ランダム性の理解」を改善する介入が必要だと結論づけています。
では、私たちは日常生活の中で、具体的にどうすればこの「脳のバグ」を補正できるのでしょうか。研究の示唆を基に、明日から使える4つの「思考フィルター」を提案します。
「あの人が言っていたから」「私には効いたから」。私たちが何かを信じるとき、その根拠の多くは「N=1(たった一つの事例)」の体験談です。
本研究が示したように、脳は「意味のある偶然」を探し求めるハンターです。たまたま神社でお参りした後に宝くじが当たれば、その前後の文脈を強引に結びつけたくなります。
【対策】
奇跡的な体験談や成功事例を聞いたときは、即座に「分母はいくつか?」と問いかけるクセをつけましょう。「お参りして宝くじが当たった人」の裏には、「お参りしたけれど外れた何千人もの人」と、「お参りしていないけれど当たった人」が存在します。
「私の体験」は強烈な感情を伴いますが、統計的には「ノイズ(雑音)」に過ぎないことが多いのです。個人の体験を「真実」ではなく、「一つの可能性(または単なる偶然)」としてフォルダ分けする冷徹さを持ちましょう。
研究で明らかになった通り、私たちは「同じことが続く」のを極端に嫌います。不運が続けば「お祓いに行かなければ」と思い、成功が続けば「自分には才能がある(またはツキが来ている)」と思い込みます。しかし、完全なランダムとは、均等に混ざり合うことではなく、「ムラ」があることなのです。
【対策】
日常で何かが連続して起きたとき、それを「流れ」と呼ぶのを一度やめてみましょう。
「悪いことが3回続いた。これは不運の連鎖だ」ではなく、「サイコロを振って1が3回続いたのと同じ確率現象が起きただけだ」と言い換えてみるのです。
「偏り」を「予兆」として捉えるのではなく、「確率のゆらぎ」として許容すること。このマインドセットがあれば、投資での短期的な値動きや、日常の小さなトラブルの連続に一喜一憂し、安易な「開運グッズ」や「必勝法」に頼るリスクを減らせます。
ホメオパシーの例のように、私たちは「したこと」と「起きたこと」を結びつけるのは得意ですが、「しなかった場合に起きたであろうこと」を想像するのは苦手です。
【対策】
「このサプリを飲んだから風邪が治った」と思ったとき、必ず「もし飲まなかったら、どうなっていただろう?」と自問してください。「飲まなくても、3日寝ていれば同じように治っていたのではないか?」という視点(比較対照の視点)を持つことが、因果関係の錯覚を断ち切る最強の剣となります。
研究者たちは、この「結論に飛びつく傾向」こそが、疑似科学信奉者の特徴であると指摘しています。一呼吸置き、あり得たかもしれない「もう一つの世界線」を想像する余裕が、判断の質を高めます。
私たちは世界に意味を求め、パターンを見出そうとする強い動機を持っています。不確実でデタラメな世界よりも、すべてが運命や陰謀でつながっている世界の方が、ある意味で「安心」できるからです。
【対策】
「偶然の一致」に感動したり、恐怖したりしている自分に気づいたら、「ああ、今私の脳は『意味』を食べたがっているな」と客観視してみてください。
感動すること自体は悪いことではありません。しかし、その感動を根拠に、高額な商品を契約したり、医療的な判断を下したりしようとしているなら、そこでブレーキを踏む必要があります。「感情的な満足」と「客観的な事実」を切り離すメタ認知能力こそが、現代のリテラシーです。

本研究が私たちに突きつけたのは、「人間は放っておくと、世界を誤って解釈するようにできている」という厳しい現実です。
ランダムな現象にパターンを見出し、単なる偶然に運命を感じる能力は、太古の昔、草むらの揺れを「風(偶然)」ではなく「捕食者(意味)」と解釈して生き延びるためには必要な生存戦略だったのかもしれません。
しかし、複雑化した現代社会において、この古い生存本能はしばしば誤作動を起こします。
効果のない医療への傾倒、科学的根拠のない健康法、SNSで拡散される陰謀論。これらはすべて、私たちの脳が「偶然の空白」に耐えられず、安易な「答え(因果関係)」を埋め込んでしまった結果と言えます。
疑似科学に惑わされない社会を目指すために必要なのは、単に怪しい情報を「デマだ」と叩いて排除することだけではありません。もっと根本的なレベルで、私たち一人ひとりが「偶然を偶然のまま受け入れる耐性」を身につけることです。
「なぜそうなったのか?」という問いに対して、「たまたまだ」「ただの偶然だ」という答えは、あまりに素っ気なく、私たちの「知りたい欲求」を満たしてはくれません。しかし、そこにある心地よい嘘(運命論や疑似科学)に逃げ込まず、「今はまだ分からない」「単なる確率のイタズラかもしれない」という不確実で中途半端な状態に留まることができる態度。それこそが、科学的な姿勢の本質であり、私たちが目指すべき「知的な強さ」なのではないでしょうか。
バルセロナ大学の研究は、私たちにこう語りかけているように思えます。
「あなたの脳は、物語を作りたがっている。でも、その物語が『事実』かどうかは、まったく別の話だ」と。
偶然の一致を楽しんでもいい。けれど、それに人生の舵取りまで任せてはいけない。その線引きができるようになったとき、私たちは初めて、自分の脳という「不完全な道具」を正しく使いこなせるようになるはずです。
[1] Applied Cognitive Psychology 「Random Sequences, Experienced Coincidences, and Pseudoscientific Beliefs」
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acp.70133
製品についてのお問い合わせやご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。
本サイトのお問い合わせフォームならびにお電話にて受け付けております。